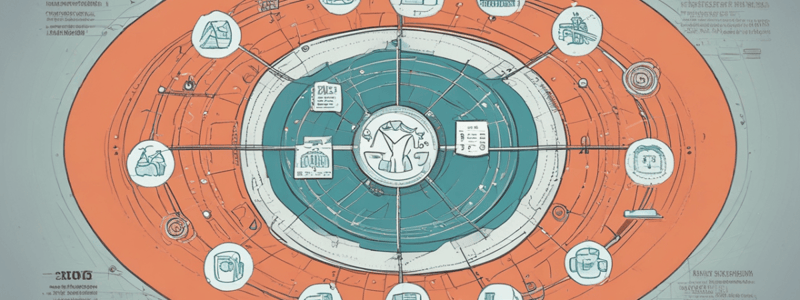Podcast
Questions and Answers
チェスター・バーナードは、組織が成立し、存続するための条件として、共通目的、協力意欲、コミュニケーションの3つの要素を挙げている。
チェスター・バーナードは、組織が成立し、存続するための条件として、共通目的、協力意欲、コミュニケーションの3つの要素を挙げている。
True (A)
個人が組織に貢献する動機は、その時の目的や欲求だけでなく、その人が利用できる他の外部機会の有無にも影響される。
個人が組織に貢献する動機は、その時の目的や欲求だけでなく、その人が利用できる他の外部機会の有無にも影響される。
True (A)
組織の有効性とは、組織の目的をどれだけ達成できたかを表すものであり、個人の貢献は組織の有効性を高めるために必須である。
組織の有効性とは、組織の目的をどれだけ達成できたかを表すものであり、個人の貢献は組織の有効性を高めるために必須である。
True (A)
組織が個人の貢献を引き出すためには、権威による強制か、個人の動機に訴えるような誘因を与える必要がある。
組織が個人の貢献を引き出すためには、権威による強制か、個人の動機に訴えるような誘因を与える必要がある。
組織均衡とは、個人の貢献がインセンティブを上回った状態を指す。
組織均衡とは、個人の貢献がインセンティブを上回った状態を指す。
無関心圏とは、組織のメンバーが上司からの命令に反問せずに受け入れる範囲のことである。
無関心圏とは、組織のメンバーが上司からの命令に反問せずに受け入れる範囲のことである。
権限受容説とは、部下が上司の命令を受け入れ、行動したときに権限関係が成立するという考え方である。
権限受容説とは、部下が上司の命令を受け入れ、行動したときに権限関係が成立するという考え方である。
意思決定には、将来の見通しが立たない場合に探索しながら意思決定を行い適応していくという機会主義的要因と、過去の歴史や経験に照らし合わせながら意思決定していくという伝統的要因がある。
意思決定には、将来の見通しが立たない場合に探索しながら意思決定を行い適応していくという機会主義的要因と、過去の歴史や経験に照らし合わせながら意思決定していくという伝統的要因がある。
バーナードは、経営者の役割を組織における道徳の創造であると定義している。
バーナードは、経営者の役割を組織における道徳の創造であると定義している。
チェスター・バーナードは、組織の維持には、個人の貢献がインセンティブを上回る必要があり、これを組織均衡と呼んでいる。
チェスター・バーナードは、組織の維持には、個人の貢献がインセンティブを上回る必要があり、これを組織均衡と呼んでいる。
チェスター・バーナードの著書『経営者の役割』は、組織の意思決定における機会主義的要因と伝統的要因の重要性を強調している。
チェスター・バーナードの著書『経営者の役割』は、組織の意思決定における機会主義的要因と伝統的要因の重要性を強調している。
松下幸之助は、その経営哲学を『水道哲学』と呼び、組織の目的達成を水道の水の流れになぞらえて説明した。
松下幸之助は、その経営哲学を『水道哲学』と呼び、組織の目的達成を水道の水の流れになぞらえて説明した。
ソニーの創業者は井深大と森田昭夫の2人で、設立趣意書では『理想工場』の建設を目標として掲げていた。
ソニーの創業者は井深大と森田昭夫の2人で、設立趣意書では『理想工場』の建設を目標として掲げていた。
チェスター・バーナードは、組織は協力体系(システム)であり、組織メンバー間の協力関係は、公式組織と非公式組織の2つの側面から成り立っている。
チェスター・バーナードは、組織は協力体系(システム)であり、組織メンバー間の協力関係は、公式組織と非公式組織の2つの側面から成り立っている。
組織の有効性とは、組織が設定した目的を達成できたかどうかを表し、個人の貢献が組織の有効性を高めるために必要である。
組織の有効性とは、組織が設定した目的を達成できたかどうかを表し、個人の貢献が組織の有効性を高めるために必要である。
個人が組織に参加する動機は、その時の目的や欲求だけでなく、その人が利用できる他の外部機会の有無にも影響される。
個人が組織に参加する動機は、その時の目的や欲求だけでなく、その人が利用できる他の外部機会の有無にも影響される。
チェスター・バーナードは、組織が成立するためには、共通目的、協力意欲、そしてコミュニケーションの3要素が必要であると主張している。
チェスター・バーナードは、組織が成立するためには、共通目的、協力意欲、そしてコミュニケーションの3要素が必要であると主張している。
チェスター・バーナードは、権限受容説を提唱し、組織のメンバーは上司からの命令に反問せずに受け入れる範囲を無関心圏と呼んでいる。
チェスター・バーナードは、権限受容説を提唱し、組織のメンバーは上司からの命令に反問せずに受け入れる範囲を無関心圏と呼んでいる。
ダイナミック・ケイパビリティは、主に個別の取引先との関係を重視する概念である。
ダイナミック・ケイパビリティは、主に個別の取引先との関係を重視する概念である。
VRIOフレームワークは、資源ベース論の主要なモデルである。
VRIOフレームワークは、資源ベース論の主要なモデルである。
資源のオーケストレーションは、企業内の資源の調和的な編成を指すが、企業外の資源は含まれない。
資源のオーケストレーションは、企業内の資源の調和的な編成を指すが、企業外の資源は含まれない。
ダイナミック・ケイパビリティは、技術や品質に関する専門的適合度と、進化的適合度の2つの視点から測定できる。
ダイナミック・ケイパビリティは、技術や品質に関する専門的適合度と、進化的適合度の2つの視点から測定できる。
共特化とは、相手企業が自社の取引のみに価値を持つ投資を行うことを指す。
共特化とは、相手企業が自社の取引のみに価値を持つ投資を行うことを指す。
ダイナミック・ケイパビリティを構成する要素には、感知、捕捉、脅威の管理・変形が含まれる。
ダイナミック・ケイパビリティを構成する要素には、感知、捕捉、脅威の管理・変形が含まれる。
企業の強みは、環境変化によって常に強みとして維持される。
企業の強みは、環境変化によって常に強みとして維持される。
デヴィッド・ティースは、ダイナミック・ケイパビリティに関する研究を提唱した。
デヴィッド・ティースは、ダイナミック・ケイパビリティに関する研究を提唱した。
経営資源とは、企業活動に不可欠な要素のことを指す。
経営資源とは、企業活動に不可欠な要素のことを指す。
Flashcards are hidden until you start studying
Study Notes
チェスター・バーナードの組織論
- 近代組織論の基礎となる理論を提示した著書『経営者の役割』において、個人と組織の意思決定に注目し、組織成立・存続の条件を明らかにした。
- 組織メンバーの協力関係を明らかにするために、組織を協力体系(システム)として理解した。
非公式組織と公式組織
- 非公式組織:友人・仲間関係などによる個人的な相互作用
- 公式組織:構造や規定など意図をもって設計された仕組み
組織の三要素
- 共通目的(組織目的)
- 協力意欲(貢献意識)
- コミュニケーション
個人の組織参加の要因
- 目的や欲求などの動機
- 外部機会の有無
組織の有効性
- 組織の目的達成度合いのことを指し、個人の貢献が必要である。
組織均衡
- 貢献≧インセンティーブの状態で、組織が維持される状態をいう。
権限
- 無関心圏:組織のメンバーが上司からの命令に反問せずに受け入れる範囲
- 権限受容説:部下が上司の命令を受け入れ、行動した時に権限関係が成立するという考え
意思決定
- 機会主義的要因:将来の見通しが立たない場合に探索しながら意思決定を行い適応していく
- 的要因:過去の歴史や経験に照らし合わせながら意思決定していく
バーナードの経営者の役割
- 組織における道徳の創造である。
松下電器とソニー
- 松下電器の創業者である松下幸之助の経営哲学は、水道哲学と呼ばれている。
- ソニーの設立者である井深大は、「自由闊達にして愉快なる理想工場の建設」を掲げていた。
チェスター・バーナードの組織論
- 近代組織論の基礎となる理論を提示した著書『経営者の役割』において、個人と組織の意思決定に注目し、組織成立・存続の条件を明らかにした。
- 組織メンバーの協力関係を明らかにするために、組織を協力体系(システム)として理解した。
非公式組織と公式組織
- 非公式組織:友人・仲間関係などによる個人的な相互作用
- 公式組織:構造や規定など意図をもって設計された仕組み
組織の三要素
- 共通目的(組織目的)
- 協力意欲(貢献意識)
- コミュニケーション
個人の組織参加の要因
- 目的や欲求などの動機
- 外部機会の有無
組織の有効性
- 組織の目的達成度合いのことを指し、個人の貢献が必要である。
組織均衡
- 貢献≧インセンティーブの状態で、組織が維持される状態をいう。
権限
- 無関心圏:組織のメンバーが上司からの命令に反問せずに受け入れる範囲
- 権限受容説:部下が上司の命令を受け入れ、行動した時に権限関係が成立するという考え
意思決定
- 機会主義的要因:将来の見通しが立たない場合に探索しながら意思決定を行い適応していく
- 的要因:過去の歴史や経験に照らし合わせながら意思決定していく
バーナードの経営者の役割
- 組織における道徳の創造である。
松下電器とソニー
- 松下電器の創業者である松下幸之助の経営哲学は、水道哲学と呼ばれている。
- ソニーの設立者である井深大は、「自由闊達にして愉快なる理想工場の建設」を掲げていた。
経営資源と組織ケイパビリティ
- 経営資源にはヒト・モノ・カネ・情報が含まれ、企業活動に不可欠。
- 組織が持つ経営資源の潜在力をパフォーマンスに変える能力を「組織ケイパビリティ」と呼ぶ。
資源ベース論とVRIOフレームワーク
- 資源ベース論は企業の競争要因を分析する理論体系。
- ジェイ・バーニーが提唱したVRIOフレームワークは、企業の資源が競争優位を生む条件を示す。
資源ベース論の欠点
- 経営資源の所有に重きを置き、資源を抱え込む戦略が強調されがち。
- 企業の強みが組織の変化を妨げる要因になる可能性がある。
- 環境変化により企業の強みが弱みになるリスクを考慮していない。
ダイナミック・ケイパビリティ
- ダイナミック・ケイパビリティは、資源を創造、拡大、修正する能力を指す。
- 市場のケイパビリティを利用し、競争環境やビジネス・エコシステムを形成することが重要。
ダイナミック・ケイパビリティの測定
- 専門的適合度(技術、品質)と進化的適合度(市場競争からの存続・成長)の2つの視点で測定。
- 高めるために、企業内外の資源を調和的に編成する「資源のオーケストレーション」が求められる。
共特化と特殊投資
- 自社だけでなく、取引先にも価値を生む特殊な投資が必要。
- 双方向の関係に基づく投資を「共特化」と呼ぶ。
ダイナミック・ケイパビリティのミクロ的基礎
- ダイナミック・ケイパビリティは3つの要素から構成される。
- 機会を同定する「感知」
- 機会を組織に落とし込む「捕捉」
- 有形・無形資産を見直す「脅威の管理・変形」
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.