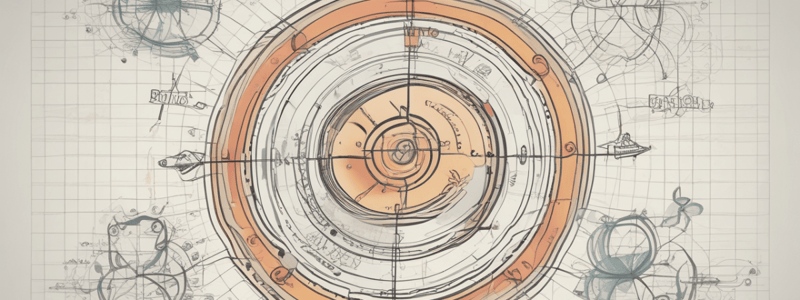Podcast
Questions and Answers
既存企業間の対抗度は、どこに影響するのか。
既存企業間の対抗度は、どこに影響するのか。
- 参入障壁
- 新規参入の脅威
- 価格競争
- 退出障壁 (correct)
何が価格競争を相対的に激化させるのか。
何が価格競争を相対的に激化させるのか。
- 参入障壁が高い
- 既存企業間の対抗度
- 退出障壁が高い (correct)
- 新規参入の脅威
何が参入障壁を高める要因であるか。
何が参入障壁を高める要因であるか。
- 流通チャネルへのアクセス
- 政府の規制や法律 (correct)
- ネットワーク外部性
- 既存企業の規模
新規参入の脅威とは何か。
新規参入の脅威とは何か。
何が流通チャネルへのアクセスを困難にするのか。
何が流通チャネルへのアクセスを困難にするのか。
何がスイッチング・コストを高めるのか。
何がスイッチング・コストを高めるのか。
何が Netzework 外部性を高めるのか。
何が Netzework 外部性を高めるのか。
何が規模の経済を高めるのか。
何が規模の経済を高めるのか。
何が特許の問題であるか。
何が特許の問題であるか。
何が新規参入の脅威を高める要因であるか。
何が新規参入の脅威を高める要因であるか。
産業集中度が高い状態では、価格競争に陥りにくい理由は何か?
産業集中度が高い状態では、価格競争に陥りにくい理由は何か?
ハーフィンダル・ハーシュマン・インデックス(HHI)が高い状態では、価格競争に陥りにくい理由は何か?
ハーフィンダル・ハーシュマン・インデックス(HHI)が高い状態では、価格競争に陥りにくい理由は何か?
スイッチングコストが低い状態では、顧客が製品を選択する基準は何か?
スイッチングコストが低い状態では、顧客が製品を選択する基準は何か?
差別化の困難性が高まる要因は何か?
差別化の困難性が高まる要因は何か?
産業集中度の尺度として、上位N社集中度やハーフィンダル・ハーシュマン・インデックス(HHI)が用いられる理由は何か?
産業集中度の尺度として、上位N社集中度やハーフィンダル・ハーシュマン・インデックス(HHI)が用いられる理由は何か?
産業集中度が高い状態では、企業は何を行うことが可能となるか?
産業集中度が高い状態では、企業は何を行うことが可能となるか?
既存企業間の対抗度が高まる要因として、どのような場合を挙げることができるか?
既存企業間の対抗度が高まる要因として、どのような場合を挙げることができるか?
ハーフィンダル・ハーシュマン・インデックス(HHI)が低い状態では、価格競争に陥りやすい理由は何か?
ハーフィンダル・ハーシュマン・インデックス(HHI)が低い状態では、価格競争に陥りやすい理由は何か?
産業集中度が高い状態では、企業は何ができるか?
産業集中度が高い状態では、企業は何ができるか?
差別化の困難性が高まる要因として、どのような場合を挙げることができるか?
差別化の困難性が高まる要因として、どのような場合を挙げることができるか?
コピー機の製品化では、1959年以降何が起こったか。
コピー機の製品化では、1959年以降何が起こったか。
ネットワーク外部性の例として挙げられるものは何か。
ネットワーク外部性の例として挙げられるものは何か。
既存企業が新規参入企業に対抗するためには何が必要か。
既存企業が新規参入企業に対抗するためには何が必要か。
スイッチング・コストとは何か。
スイッチング・コストとは何か。
新規参入企業が苦労する理由として挙げられるものは何か。
新規参入企業が苦労する理由として挙げられるものは何か。
製品差別化が可能にする要因として挙げられるものは何か。
製品差別化が可能にする要因として挙げられるものは何か。
新規参入企業が苦労する理由として、製品差別化の程度が高い場合の影響とは何か。
新規参入企業が苦労する理由として、製品差別化の程度が高い場合の影響とは何か。
資本の大小が新規参入企業に与える影響とは何か。
資本の大小が新規参入企業に与える影響とは何か。
資本コストとは何か。
資本コストとは何か。
既存企業が新規参入企業に対抗するためには何が必要か。
既存企業が新規参入企業に対抗するためには何が必要か。
新規参⼊企業が既存企業に劣るときの理由として適切なものは何ですか。
新規参⼊企業が既存企業に劣るときの理由として適切なものは何ですか。
規模の経済が強く効く産業での参⼊の困難について適切な理由は何ですか。
規模の経済が強く効く産業での参⼊の困難について適切な理由は何ですか。
規模でライバルに追いつくまでの期間中に、当該事業は何になるか。
規模でライバルに追いつくまでの期間中に、当該事業は何になるか。
技術⾰新により代替品が登場することで、従来からある産業の占有価値が低下する理由は何ですか。
技術⾰新により代替品が登場することで、従来からある産業の占有価値が低下する理由は何ですか。
代替品とはどのような財ですか。
代替品とはどのような財ですか。
新規参⼊企業が既存企業に劣るとき、どのような劣位に陥る傾向にあるか。
新規参⼊企業が既存企業に劣るとき、どのような劣位に陥る傾向にあるか。
規模でライバルに追いつくまでの期間中、当該事業は何のリスクにさらされるか。
規模でライバルに追いつくまでの期間中、当該事業は何のリスクにさらされるか。
代替品の脅威の度合いとは何ですか。
代替品の脅威の度合いとは何ですか。
供給業者と顧客の交渉力を構成する要素とは何か?
供給業者と顧客の交渉力を構成する要素とは何か?
顧客が交渉力を有すると、産業の占有価値はどうなるか?
顧客が交渉力を有すると、産業の占有価値はどうなるか?
供給業者の交渉力を左右する要因とは何か?
供給業者の交渉力を左右する要因とは何か?
供給業者の潜在的な交渉力の基盤を高める要因とは何か?
供給業者の潜在的な交渉力の基盤を高める要因とは何か?
顧客の交渉力を高める要因とは何か?
顧客の交渉力を高める要因とは何か?
交渉力を強化することは、企業合併が行われる理由のひとつであるというのは何を指すのか?
交渉力を強化することは、企業合併が行われる理由のひとつであるというのは何を指すのか?
産業の占有価値を巡る外部との戦いとは何か?
産業の占有価値を巡る外部との戦いとは何か?
供給業者が垂直統合する可能性が上昇すると、交渉力はどうなるか?
供給業者が垂直統合する可能性が上昇すると、交渉力はどうなるか?
顧客が交渉力を利 dụngする意志を高める要因とは何か?
顧客が交渉力を利 dụngする意志を高める要因とは何か?
交渉力を強化することとは、どのような戦略的資材調達を指すのか?
交渉力を強化することとは、どのような戦略的資材調達を指すのか?
導入期における顧客は、革新的もの好きじゃない。
導入期における顧客は、革新的もの好きじゃない。
普及のボトルネックを取り払うためには、普及のボトルネックを特定する必要がある。
普及のボトルネックを取り払うためには、普及のボトルネックを特定する必要がある。
補完財とは、単独ではなく他の製品やサービスと組み合わされることで価値を増す財である。
補完財とは、単独ではなく他の製品やサービスと組み合わされることで価値を増す財である。
スイッチング・コストが低い状態では、顧客が製品を選択する基準はない。
スイッチング・コストが低い状態では、顧客が製品を選択する基準はない。
ネットワーク外部性とは、製品やサービスの価値が増えるほど顧客が増えるという現象である。
ネットワーク外部性とは、製品やサービスの価値が増えるほど顧客が増えるという現象である。
規模の経済が強く効く産業での参入は容易である。
規模の経済が強く効く産業での参入は容易である。
技術の進歩による代替品の登場は、従来からある産業の占有価値を高める。
技術の進歩による代替品の登場は、従来からある産業の占有価値を高める。
顧客の交渉力が高まるにつれて、供給業者の交渉力も高まる。
顧客の交渉力が高まるにつれて、供給業者の交渉力も高まる。
導入期における企業の課題とは、普及のボトルネックを特定し、それを取り払うことである。
導入期における企業の課題とは、普及のボトルネックを特定し、それを取り払うことである。
上澄み価格政策とは、低価格政策であり、新規参入企業に対抗するために用いられる。
上澄み価格政策とは、低価格政策であり、新規参入企業に対抗するために用いられる。
液晶ディスプレイ技術の流出が生じた場合、自社の上流活動の規模が小さいほうが良い。
液晶ディスプレイ技術の流出が生じた場合、自社の上流活動の規模が小さいほうが良い。
上流/下流活動に求める内容が特異的な場合、内部調達のほうが望ましい。
上流/下流活動に求める内容が特異的な場合、内部調達のほうが望ましい。
関係特殊的投資が果たされるためには、上流/下流活動との取引が安定的であるという保証が不可欠である。
関係特殊的投資が果たされるためには、上流/下流活動との取引が安定的であるという保証が不可欠である。
直接的な費用とは、規模の影響を受ける費用であり、内部管理コストや取引コストを含まない。
直接的な費用とは、規模の影響を受ける費用であり、内部管理コストや取引コストを含まない。
取引コストが高まる理由として、売買される財について情報の非対称性が存在する場合がある。
取引コストが高まる理由として、売買される財について情報の非対称性が存在する場合がある。
垂直的範囲の決定において、make/buyの選択は②や④だけで判断することができる。
垂直的範囲の決定において、make/buyの選択は②や④だけで判断することができる。
ネットワーク外部性が高まる要因として、差別化の困難性を挙げることができる。
ネットワーク外部性が高まる要因として、差別化の困難性を挙げることができる。
内部管理コストは、規模が大きいほど低くなる。
内部管理コストは、規模が大きいほど低くなる。
規模の経済が強く効く産業での参⼊は困難である。
規模の経済が強く効く産業での参⼊は困難である。
間接的な費用とは、内部管理コストや取引コストを含まない。
間接的な費用とは、内部管理コストや取引コストを含まない。
スイッチング・コストが高まる要因として、規模の経済を挙げることができる。
スイッチング・コストが高まる要因として、規模の経済を挙げることができる。
取引コストが高くなる場合、取引される財が複雑な場合である。
取引コストが高くなる場合、取引される財が複雑な場合である。
垂直的範囲の決定において、make/buyの選択は、活動内容やそれを取り巻く外部環境に影響される。
垂直的範囲の決定において、make/buyの選択は、活動内容やそれを取り巻く外部環境に影響される。
交渉力を強化することは、企業合併が行われる理由のひとつである。
交渉力を強化することは、企業合併が行われる理由のひとつである。
顧客が交渉力を有すると、産業の占有価値が高まる。
顧客が交渉力を有すると、産業の占有価値が高まる。
技術⾰新により代替品が登場することで、従来からある産業の占有価値が高まる。
技術⾰新により代替品が登場することで、従来からある産業の占有価値が高まる。
規模の経済が強く効く産業では、新規参⼊企業が苦労する理由の一つとして、製品差別化の困難性を挙げることができる。
規模の経済が強く効く産業では、新規参⼊企業が苦労する理由の一つとして、製品差別化の困難性を挙げることができる。
供給業者が垂直統合する可能性が上昇すると、交渉力が低下する。
供給業者が垂直統合する可能性が上昇すると、交渉力が低下する。
ハーフィンダル・ハーシュマン・インデックス(HHI)が高い状態では、新規参⼊企業が苦労する理由の一つとして、規模の経済の困難性を挙げることができる。
ハーフィンダル・ハーシュマン・インデックス(HHI)が高い状態では、新規参⼊企業が苦労する理由の一つとして、規模の経済の困難性を挙げることができる。
多⾓化の理由として、リスクヘッジを挙げることができる。
多⾓化の理由として、リスクヘッジを挙げることができる。
経営戦略とは、組織活動の基本的方針と環境のかかわりにおいて示すものである。
経営戦略とは、組織活動の基本的方針と環境のかかわりにおいて示すものである。
事業戦略は、企業の成長を左右するという意味で、その設定は、経営陣にとって重要なタスクである。
事業戦略は、企業の成長を左右するという意味で、その設定は、経営陣にとって重要なタスクである。
多角化とは、無関係な事業への参入をいう。
多角化とは、無関係な事業への参入をいう。
垂直統合とは、前方統合や後方統合をいう。
垂直統合とは、前方統合や後方統合をいう。
ドメイン・コンセンサスとは、企業のドメインについて、企業と外部主体の合意をいう。
ドメイン・コンセンサスとは、企業のドメインについて、企業と外部主体の合意をいう。
多角化の目的の一つは、リスクヘッジである。
多角化の目的の一つは、リスクヘッジである。
製品ライフサイクルとは、製品が販売されてからの経過時間によって、生みのたれ方を示す曲線である。
製品ライフサイクルとは、製品が販売されてからの経過時間によって、生みのたれ方を示す曲線である。
スイッチング・コストとは、顧客が製品を選択する基準である。
スイッチング・コストとは、顧客が製品を選択する基準である。
ネットワーク外部性とは、顧客がすでに持っている製品やサービスによって、新しい製品やサービスの需要を増大させることをいう。
ネットワーク外部性とは、顧客がすでに持っている製品やサービスによって、新しい製品やサービスの需要を増大させることをいう。
規模の経済とは、企業の規模が大きくなるとコストが低下することをいう。
規模の経済とは、企業の規模が大きくなるとコストが低下することをいう。
導入期においては、顧客のニーズは高水準である。
導入期においては、顧客のニーズは高水準である。
成長期においては、顧客のニーズは高水準である。
成長期においては、顧客のニーズは高水準である。
衰退期においては、企業のシェアは減少する。
衰退期においては、企業のシェアは減少する。
導入期においては、企業の利益は高い。
導入期においては、企業の利益は高い。
成長期においては、顧客のニーズは低水準である。
成長期においては、顧客のニーズは低水準である。
衰退期においては、新規参入の脅威は低い。
衰退期においては、新規参入の脅威は低い。
導入期においては、顧客の知識は低水準である。
導入期においては、顧客の知識は低水準である。
成長期においては、顧客の知識は高水準である。
成長期においては、顧客の知識は高水準である。
衰退期においては、企業のシェアは固定される。
衰退期においては、企業のシェアは固定される。
導入期においては、流通チャネルのアクセスが容易である。
導入期においては、流通チャネルのアクセスが容易である。
Flashcards are hidden until you start studying
Study Notes
産業構造分析
1. 産業集中度の低い (企業数と規模の分布)
- 産業集中度が低いほど、競争が激しくなる
- 小規模の企業の存在により、競争が激化する
2. 差別化の困難性が高い (コモディティ化)
- 製品やサービスの差別化が困難であるほど、価格競争に陥りやすい
- コモディティ化により、価格競争が激化する
3. スイッチングコストが低い
- スイッチングコストが低いほど、顧客が容易に他の企業に移動することができる
- 競争が激化する
4. 当該産業の戦略的な価値が高い
- 当該産業の戦略的な価値が高いほど、企業は競争を生き延びることができる
- 価値が高いほど、競争が激化する
5. 企業バックグラウンドの多様性が高い
- 企業バックグラウンドの多様性が高いほど、競争が激化する
- 多様性が高いほど、企業間の競争が激化する
産業集中度の尺度
- 上位N社集中度 (Herfindahl-Hirschman Index)
- 上位1社集中度、上位3社集中度、上位5社集中度など
供給構造に影響を及ぼす要因
- 産業成長率が低い
- 生産能力拡大が小刻みである
- 固定費・在庫費用が高い
- 退出障壁が高い
差別化の次元
- 製品内の属性 (機能、品質、デザイン)
- 製品外の属性 (イメージ、ブランド、納期)
スイッチングコスト
- 利用している製品を変更する際の費用
- 金銭的な費用だけでなく、時間的・人的費用も含む
退出障壁
- 当該産業から撤退できない理由
- 事業の売却が困難、設備や人的資源が他の企業・産業に転用できない
新規参入の脅威
- 政府の規制や法律
- 流通チャネルへのアクセスの難易度
- ネットワーク外部性
- スイッチングコスト
- 製品差別化の程度
- 投下資本の大きさ
- 規模の経済
交渉力
- 供給業者の交渉力 (売方の交渣力)
- 顧客の交渉力 (買方の交渣力)
- 顕在化する交渉力 (説得力)
- 潜在的な交渉力の基盤 (potency)
- 交渉力を活用ろうとする意志 (credibility)
供給業者の交渉力
- 供給業者の潜在的な交渉力の基盤を高める要因
- 供給業者が所属する産業の産業集中度
- 供給業者が供給する財の差別性
- 供給業者が供給する財に対する代替品の種類/数
- 供給業者にとって当該産業の重要性
- スイッチングコスト
- 供給業者の交渉力を利用する意志を高める要因
- 供給業者の売上のうち当該産業への売上が占める割合
- 供給業者の利益水準
- 供給業者が垂直統合する可能性
顧客の交渉力
- 顧客の潜在的な交渉力の基盤を高める要因
- 顧客が所属する産業の産業集中度
- 供給業者が供給する財の差別性
- 供給業者が供給する財に対する代替品の種類/数
- 顧客にとって当該産業の重要性
- スイッチングコスト
- 顧客の交渉力を利用する意志を高める要因
- 顧客のコストに占める当該産業の売上の割合
- 顧客の利益水準
- 顧客が垂直統合する可能性
経営戦略の基本
- 経営戦略とは、企業の基本的な方向性を環境との関わりにおいて示すものである。
- 経営戦略の目標は、特定の目的に達するための道筋を考えるうえで、役立つ概観を行うものである。
経営戦略の階層性
- 企業戦略(corporate strategy)と事業戦略(business strategy)の違い
- 企業戦略:企業の成長・事業の選択
- 事業戦略:特定の事業活動での利益獲得
事業戦略
- 事業活動の拡大
- 横方向の拡大=多角化
- タテ方向の拡大=垂直統合
- 事業ポートフォリオ
- 企業が保持する複数の事業活動のポートフォリオ
ドメイン・コンセンサス
- 企業ドメインの設定
- 企業の活動領域を企業側が決めたところで、企業活動に関わる外部主体の合意・理解がなければ、その活動は成功しない。
- ドメイン・コンセンサスの重要性
- 企業ドメインの設定と事業戦略との関係
多角化
- 多角化の種類
- 関係ある事業への多角化=関連型多角化
- 無関係な事業への多角化=非関連型多角化
- 多角化の目的
- リスクの分散
- 成長機会の追求
- 経営資源の有効活用
製品ライフサイクル
- 製品ライフサイクルとは、製品の生みのうち、寿命を迎えるものである。
- 製品ライフサイクルと多角化
- 既存の製品市場が成熟期・衰退期を迎えると、既存事業の売上等は停滞・低下する。
- この時点で、製品市場が成長期を迎えている事業を保有すれば、企業規模の停滞・低下を補うことができる。### 導入期・成長期の事業を持ち出す
- モチベーションの低下を避けるために、有望な事業領域に参入しておくこと。
多様化の目的③
- 範囲の経済が生み出す理由
- 経営資源の有効活用
- 既存事業における未利用資源の存在
- 新事業のコスト削減
範囲の経済の背景
- 相乗効果(シナジー効果)
- 2つの事業で利 用されることで、ある経営資源の価値がより高くなること
- 遊休経営資源=使われずに残っている経営資源
- 相補効果(コンプリメント効果)
- 2つの事業で利 用されることで、ある経営資源の価値が無駄な利 用されること
competitive power
- 情報的経営資源の同時多重利 用
- 技術的なノウハウ
- 顧客の信用
- 流通チャネルの支配力
- 経営ノウハウ
- ダイナミック・シナジー
- 事業展開のプロセスで新たに情報的経営資源の蓄積が行われ、蓄積された情報的経営資源をもとにして、新たな事業展開が進められる
多様化の理由を巡るトピックス①
- 三つの理由
- リスクヘッジ
- 成長機会の追求
- 経営資源の有効活用
- ダイナミック・シナジー
多様化の理由を巡るトピックス②
- 専門化によって遊休経営資源が生じる
- 学習の経済
- 技術やブランドの蓄積・成長
- 専門化 → 競争地位 → 資源
- Penrose(1959)の理論
- 経営資源と外部環境の状況
多様化の注意点
- 多様化か、専門化か、という問題に対する絶対的な正解は存在しない
- 企業(経営陣)は、自社の置かれた状況(経営資源と外部環境)を鑑み、いずれが必要な段階なのかを判断しなければならない
- 多様化→専門化→多様化→…というサイクルによって、企業は成長する
価値体系(value system)
- 特定の消費財がわれわれの手に渡るまでには、様々な活動が展開されている
- われわれ消費者は、財・サービスから便益を得ている
垂直統合とアウトソース
- 上流/下流活動において競争圧力が働いているか否か
- 関係特殊的投資
- 活動Aが特異的な場合、活動Aに最適化した上流/下流の活動が展開される
- 上流/下流活動に求める内容(質)が一般的な場合、外部調達の方法が望ましい
- 上流/下流活動に求める内容が特異的な場合、内部調達の方法が望ましい
関係特殊的投資
- 上流/下流の特異的な活動が展開される(関係特殊的投資が果たされる)ためには、当該活動Aとの取引が安定的であるという保証が不可欠
- 特異的な活動については、ホールドアップ問題が生じることで、外部調達が難しい場合がある
直接的な費用
- 活動Aが特異的な場合、関係特殊的投資は果たされない
- 上流/下流活動に求める内容(質)が一般的な場合、外部調達の方法が望ましい
間接的な費用
- 内部管理コスト
- 調整・コミュニケーションに係る費用
- 何をどれだけ作るのか
- 取引コスト
- 取引がきちんとおこなわれるために必要なコスト
- 取引の不確実性が高くなる場合、取引コストが高くなる
まとめ
- 垂直的範囲の決定
- 価値体系のどこからどこまでを自社で手にけ、どこからを他社に委ねるか
- 個々の上流/下流活動についての要因を検討し、make/buyの何れが合理的かを総合的に判断しなければならない### 製品ライフサイクルとは
- 製品市場の規模の経時的変化:S字型を描く場合が多い
- この市場規模の変化は、事業環境の変化を意味する
- 競争の状況、顧客の特徴も影響する
製品ライフサイクルの背景
- 導入期:顧客によって違う
- 成長期:技術の発展によって旧製品が駆逐される場合がある
- 成熟期:飽和、売上が低下する
- 衰退期:購入が減少、売上が低下する
製品ライフサイクルの段階別の特徴と
- 導入期:
- 特徴:低水準、利益がマイナスor僅か
- 競争:殆どなし
- 顧客:革新者/マニア
- 戦略の焦点:市場の拡大
- 成長期:
- 特徴:急速上昇、利益のピーク
- 競争:増大
- 顧客:マス・マーケット
- 戦略の焦点:市場浸透
- 成熟期:
- 特徴:緩慢な上昇、利益の低下
- 競争:競合者多数
- 顧客:マス・マーケット
- 戦略の焦点:シェア防衛
- 衰退期:
- 特徴:下降、利益の低下
- 競争:減少
- 顧客:遅滞者
- 戦略の焦点:撤退時期
導入期における企業の課題
- 普及のボトルネックを取り払う
- 市場規模が小さすぎる問題
- 普及の阻害要因:購買者側、生産者側、他の要因
普及の阻害要因
- 購買者側:購買にあたるまでの意思決定プロセス、偏見、価値(効用)を感じない
- 生産者側:生産体制が未整備、流通網の確立、価格の高さ
- その他の要因:ネットワーク外部性、補完財が未発達
補完財の提供を巡る選択肢のメリット・デメリット
- 補完財を提供することで製品の価値を高めることができる
- しかし、自社で補完財を提供するか、他社に提供してもらうかという選択肢がある
- 各選択肢のメリット・デメリットを考慮する必要がある
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.